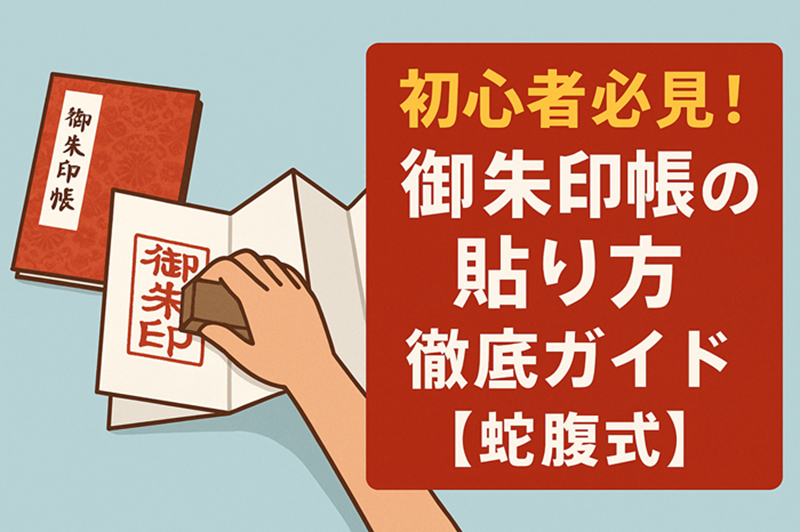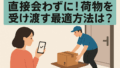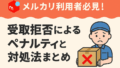御朱印帳は神社やお寺でいただく御朱印を美しく残すための大切な帳面ですが、初めて扱う方にとっては「どう貼ればよいのか」「順番はどうするのか」と迷ってしまうことも多いものです。
本記事では、初心者向けに蛇腹式御朱印帳の貼り方を詳しく解説します。
ページの順番や裏面の使い方、のりの選び方や失敗例、さらに保管やマナーまで、御朱印帳ライフを楽しむためのポイントを徹底ガイドします。
これを読めば、御朱印帳を宝物のように美しく整理できるようになります。
御朱印帳って何?初心者が知っておくべき基本知識
御朱印帳の役割と歴史
御朱印帳(ごしゅいんちょう)とは、神社やお寺でいただける「御朱印」を集めて記録していくための専用の帳面です。
御朱印は墨で寺社名や参拝日を書き、朱色の印が押されたもので、単なるスタンプとは異なり、参拝をしたことを証明する神聖な印でもあります。
その起源は古く、もともとは参拝者が写経を納めた際に「確かにお経を納めました」という証明としていただいていたものです。
その後、参拝や信仰の証として広く授与されるようになり、現在では参拝の記念や旅の思い出として御朱印を集める人が増えています。
御朱印帳はその大切な証をきれいに残すための宝物のような存在なのです。
種類別:御朱印帳のデザインとサイズ
御朱印帳には主に蛇腹式と綴じ式の2種類があります。
蛇腹式(じゃばらしき)
紙が屏風のようにつながって折りたたまれており、広げると連続した御朱印を見開きで鑑賞できます。
書き置きの御朱印を貼りやすく、複数の御朱印を並べて楽しめる点が人気です。
綴じ式(とじしき)
本のように糸や糊で綴じられたタイプで、ページをめくる感覚で御朱印を楽しめます。
サイズがコンパクトなので持ち歩きやすく、旅行やお出かけの際に便利です。
デザインは神社やお寺ごとに個性があり、和柄や花柄、動物モチーフ、地域限定デザインなど多彩です。
サイズも片手に収まる小型から、御朱印を大きく楽しめる大判までそろっています。
初心者はまず「持ち歩きやすさ」と「気に入ったデザイン」で選ぶのがおすすめです。
神社や仏閣での御朱印の受取方法
御朱印をいただく際には、必ず「参拝を先に行う」ことが大切です。
お参りを済ませたあとに御朱印所へ行き、御朱印帳を預けて書いていただきます。
ただし、すべての寺社が御朱印帳への直書きに対応しているわけではありません。
混雑時や特別行事の際は「書き置き」と呼ばれる紙に書かれた御朱印が授与されることもあります。
その場合は自宅で御朱印帳に貼り付けて保管します。
御朱印の受付時間や初穂料(料金)は寺社ごとに異なるため、事前に公式サイトや案内を確認しておくと安心です。
御朱印帳の貼り方基本ガイド
蛇腹式御朱印帳の特徴とメリット
蛇腹式御朱印帳は、ページが連続して折りたたまれているため、御朱印を貼ったときに段差が出にくく、美しくまとまります。
また、広げると複数の御朱印を横並びで鑑賞できるので、旅の記録や神社巡りの成果を一覧できるのも大きな魅力です。
表面を使い切ったら裏面も利用できるため、収納できる御朱印の数が多いのもメリットのひとつです。
貼り方のSTEP BY STEPガイド
御朱印をきれいに貼るための基本手順は次の通りです。
1.貼る位置を決める
御朱印帳のどのページに貼るかを確認します。
蛇腹式の場合は表面を順番に埋めていくのが基本です。
2.御朱印のサイズを整える
書き置き御朱印は紙の周りに余白があることが多いので、必要に応じてカッターやはさみで余白をカットして整えます。
3.のりを塗る
御朱印の四隅と中央に均一にスティックのりを塗ります。
端をしっかり固定することで、めくれてしまうのを防げます。
4.御朱印帳に貼る
位置を合わせながらゆっくりと置き、上から指やヘラで軽く押さえながら空気を抜いていきます。
この手順を守れば、紙の浮きやシワを最小限に抑え、美しく貼ることができます。
のりの使い方と注意点
のり選びも御朱印帳を長持ちさせるポイントです。
・スティックのり:均一に塗りやすく、紙が波打ちにくい
・アシッドフリーののり:酸を含まないため紙の劣化を防ぎ、長期間保存に適している
・液体のりは避ける:水分が多いため、紙がヨレたり波打ったりしやすい
また、のりがはみ出すと御朱印や隣のページにシミができることがあります。
はみ出した場合は、すぐにティッシュや綿棒で拭き取りましょう。
仕上げに文鎮や重しをのせてしばらく乾かすと、より平らに仕上がります。
御朱印帳のページ構成と順番
最初のページはどうする?
御朱印帳の最初のページには、特別な意味があります。
多くの人は「初めて参拝した神社」や「特に思い入れのあるお寺」の御朱印を最初に貼ります。
最初のページをお気に入りの御朱印で飾ることで、後から御朱印帳を開いたときに、そのときの感動や思い出を振り返りやすくなります。
また、最初のページに貼る際は、見開きで美しく収まる位置に調整しましょう。
特に蛇腹式御朱印帳の場合、最初にきれいに貼ることで、その後のページも整った印象になります。
裏面のお札や書き置きの扱い
蛇腹式御朱印帳は両面を使うことができますが、基本的には表面を使い切ってから裏面に貼るのが一般的です。
裏面の活用例
・お札や書き置きの御朱印をまとめて貼る
・特別な参拝記念の御朱印を貼る
・前のページと関連する御朱印を並べる
こうすることで、ページ構成が整理され、見開きで見たときに視覚的にもすっきりします。
ページを飛ばさないためのルール
御朱印帳の順番を飛ばしてしまうと、後から整理するのが大変になります。
特に蛇腹式はページが連続しているため、途中に空白があると見栄えが悪く、後から追加で貼るとバランスが崩れやすくなります。
ポイント
・常に前から順番に貼る
・空白ページを作らない
・書き置き御朱印も順番に合わせて貼る
これらのルールを守るだけで、きれいで見やすい御朱印帳を作ることができます。
貼り方でやってはいけない事
左開きにしてしまった時の対処法
御朱印帳は基本的に右開きで使います。
間違えて左開きにしてしまった場合は、無理に戻すのではなく、次のように対応すると良いです。
・そのページを最後に回す
・裏面を利用して順番を調整する
無理に剥がすと紙が破れたり、御朱印が汚れる原因になるため注意してください。
間違った順番で貼った時の修正方法
万一、間違えて貼ってしまった場合は、焦らず以下の方法で修正します。
・御朱印の上から和紙や台紙を貼って新しい御朱印を重ねる
・無理に剥がさない(紙や墨が傷む可能性が高い)
・そのページを「記念ページ」として残す方法もある
このように工夫すれば、見栄えも美しく、失敗をカバーできます。
ノリを使った際の失敗事例
初心者に多い失敗としては、
・液体のりで紙が波打つ
・のりがはみ出して御朱印が汚れる
などがあります。
対策
・スティックのりを使用する
・両面テープを活用する
・貼った後に文鎮や重しを置き、しっかり乾かす
これだけで、紙の歪みや汚れを防ぎ、美しい仕上がりになります。
御朱印帳の保管とマナー
保管に適した環境と道具
御朱印帳は紙製品なので、湿気や直射日光は大敵です。保管する際は以下を意識しましょう。
・湿気の少ない場所に置く
・ブックカバーや専用袋で保護する
・長期保存する場合は、乾燥剤を入れて湿度管理をする
こうすることで、墨や朱印の色褪せを防ぎ、長く美しく保つことができます。
参拝後の御朱印帳の扱い方
参拝後にすぐバッグにしまうのではなく、まず墨が乾いているか確認してから片付けましょう。
インクが乾かないうちに折りたたむと、御朱印がにじむ原因になります。
マナー違反を避けるためのポイント
御朱印は「スタンプラリー」ではなく、あくまで信仰の証です。
・参拝をせずに御朱印だけを求めるのはマナー違反
・受け取る際には礼拝を済ませ、感謝の気持ちを忘れない
・他の参拝者の迷惑にならないよう静かに受け取る
これらを守ることで、御朱印帳がただのコレクションではなく、信仰の記録として意味のあるものになります。
まとめ
初心者にオススメの御朱印スポット
・東京:明治神宮、浅草寺
・京都:清水寺、伏見稲荷大社
これらは御朱印対応が丁寧で、初めての御朱印帳にも最適です。
御朱印集めは、参拝の記録を自分だけの形で残せる楽しみがあります。
ページを開けば、その日の参拝の思い出や旅の記録を振り返ることができます。
御朱印帳は単なるコレクションではなく、信仰や旅の記録そのものです。
正しい貼り方や順番を意識することで、長く大切に残せる「宝物」にすることができます。
初心者向けに蛇腹式御朱印帳の貼り方を徹底解説。ページの順番、裏面の使い方、のりの選び方や失敗例、保管方法やマナーまで詳しく紹介します。これから御朱印帳を始める方必見のガイドです。